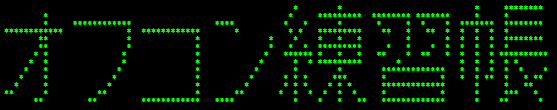NECのオフコン情報掲示板(いろいろ)
| NECのオフコンに関しての最新情報、面白い話、昔の思い出、何でも自由に書いてください。 |
| 新規投稿 | スレッド表示 | ツリー表示 | 投稿順表示 | i-mode | トップ |
| ■▲▼ | ||
| 1 | 過去の生産終了までの期間について | |
| み 2005-7-5 21:41:00
[返信] [編集] お世話になります。 東芝のTPや日本電気のN5200のメーカー生産終了宣言から実際の供給終了までの期間をご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。 今後の参考になるかなと思いまして。 | ||
| 2 | Re:過去の生産終了までの期間について | |
| ターラヤン 2005-7-8 2:46:00
[返信] [編集] 普通、新発売は大々的に宣伝しますが、生産終了の方は告知もせずにひっそりと終わることが多いので、よくわかりません。 ・TP90 2001年11月12日に以下の記事が載っています。 ---- 東芝と日本IBMは2001年11月12日、SI事業での提携を強化すると発表した。 東芝は日本IBMのサーバー製品「eServer」の販売を開始する。 〜中略〜 また、東芝の オフコン 「TPシリーズ」の後継機として日本IBMの「eServer iSeries(旧:AS/400)」も販売する。 ---- 上記を見る限り、事実上の生産終了宣言のように思われますが、実は今もTP90Fシリーズは販売しています。 (既存ユーザの買い替え専用として。) ・N5200 生産終了宣言がなされたかどうかは不明。 純正のN5200シリーズは97年3月で出荷停止。 PC−PTOSは、PC9801とハードが共通なので、PC9801と同じく2003年が出荷停止の年。 ・PC9801(参考) http://www.express.nec.co.jp/care/pctechinfo/pc9800.html 2003年8月7日にHP掲載 2003年9月30日受注終了 ちなみに補修用性能部品の最低保有期間は、生産打切後7年間 おそらく関係者や大口のユーザにはもっと前から通知していると思いますが、そこまではわかりません。 | ||
| 全部読む 最新50 1-100 板のトップ リロード | ||
| ■▲▼ | ||
| 1 | オープンシステムのレガシー化 | |
| 0e0e 2005-7-1 11:35:00
[返信] [編集] 面白い話題が多くて勝手にRESつけさせてもらってますが、ご挨拶が遅れました。 はじめまして0e0eです。オフコン経験は長いですがわからないことも多々あると思いますのでよろしくお願いします。 早くも、ハード的にはNT4.0サーバ、Win95,98クライアントで動いているようなオープンシステム、16bit開発言語など今では使われなくなった言語で作られたオープンシステムが導入後5年程度でレガシー化しています。 それに比べてAVX COBOLで作成されたシステムは10年以上前の開発ベースであってもしっかりメンテされていれば日々進化して、今でも現役で動いています。オフコンシステムがレガシー化するのは人的問題が大きいのかな?って思っています。 | ||
| 2 | Re:オープンシステムのレガシー化 | |
| BLUELION 2005-7-4 9:28:00
[返信] [編集] はじめましてbluelionです うーーん 個人的にはOS(WINDOWS)の陳腐化が一番の原因だと思っています セキュリティーの問題などをMSがサポートしないとなるとシステム管理者としては使い続くることに問題を感じますからね OSとしてのA−VXはNECが継続してメンテしてくれるのでその点は安心です ただし最近どうも技術者がすくないらしいと販売店はいっていますけど | ||
| 3 | Re:オープンシステムのレガシー化 | |
| 0e0e 2005-7-4 10:07:00
[返信] [編集] bluelionさんこんにちは そうですね、古いOS、開発言語をいつまでサポートしてくれるか?ってところですね。 AVXはユーザーがいる限り作り続けるとメーカー側は言ってるみたいですが積極的に拡大しようという方針にはなっていない印象なのが残念です。 N5200、PC98のときもそんなこと言ってたような記憶ですのである程度大口ユーザーが無くなってしまったら切り捨てられるかもしれないという不安が・・・ | ||
| 4 | Re:オープンシステムのレガシー化 | |
| オフコン人 2005-7-5 22:58:00
[返信] [編集] 皆さんのおっしゃるのも理解できます。 しかし、NetWareはどうだったんでしょうか? Windowsもバカにして、今やサポートできる人は皆無に近いのじゃないでしょうか。 開発言語が古い? COBOL85ですか? 何か間違っておられるような気がします。 ダウンサイジングが良くて、C/Sが良くて、TSになり、MetaFrameですか? オープンシステム、Windowsのこと? 違うでしょ。 あ?、皆、もっと真剣に自分のシステムを見直しませんか? | ||
| 5 | Re:オープンシステムのレガシー化 | |
| Bluelion 2005-7-6 2:34:00
[返信] [編集] CBL85なんてずっと仕様が変わっていないし 下位互換もあっていい言語だと思いますが 将来的にCBL85がAVXでサポートされるのかな? って思うことがあります。 それでCOBOLならまだ、いいほうでSMART2とかの簡易言語だとさらに???ってなりませんか? 実際古いVERのAVXだと、不具合を報告してもレスポンスかなり悪い感じがします。 まーそれでもAVX上ならなんとか回避策を考えられるのでいいんですけど Windowsだとブラックボックスが多すぎて... | ||
| 全部読む 最新50 1-100 板のトップ リロード | ||
| ■▲▼ | ||
| 1 | A−VX on Windowsは中途半端だ!! | |
| EXCHANGE 2005-3-14 6:26:00
[返信] [編集] * 現在、600シリーズのA−VXは、WindowsServerの上で動作しており、Windows上のミドルウエアということになっている。 * このような方式を使っているのはいくつかの理由があるかと思われる。 (1)Intel系のCPU上でA−VXを動かすため。逆に見れば、Windowsをファームウエアとして使うことで、A−VXをIntel系CPU上で動作させている、ともいえる。 (2)ハードウエアを含むサーバの管理ツールに、他のIAサーバと同じツールが使える、など NEC側の開発効率化。 (3)上記による、IAサーバ製品全体の一体感。 (4)販売に際して、「もはやオフコンではない」と印象づけられる。 といったところであろうか。 * そして、この方式(A−VX on Windows)によって、まるでA−VXとWindowsソフトウエアが両方動作出来るとの印象を与えているのも事実である。 * だが、A−VXで開発運用していて、いつも感じることだが、 「結局は、A−VXとしてしか使えない」と思ってしまうのである。 原因はいくつかある。 (1)Windows上で動作するソフトを同一サーバ上で稼働させようとしても、CPU、メモリの配分が計画できないので、 不安定になるおそれがある。 (2)追加メモリ、追加CPUが他のExpressサーバ(100シリーズ)に比べてあまりに高価に設定されていて、別サーバを購入した方が安価になってしまう。 * NECのACOS、IBMのiseriesなど主要なホスト系マシンはハード的、もしくは論理的に1台のマシンを複数の区画に分割してそれぞれで「従来ホストOS」「Windows」「Linux」などを同時に稼働させる方式をとるようにするのがトレンドだ。 * 600シリーズも、A−VXをWin上で稼働させる等と言うことやめて、 (1)IntelのCPU上に独自のファームウエアをかませてA−VXを稼働させ、 (2)複数区画方式を採用して、A−VXの稼働する区画、Windowsの稼働する区画(複数も可)、 などといった、やり方に変える方が賢明であると思う。 * こうすれば、A−VX区画は、windowsのセキュリティ問題から解放され、windows区画ではoracleなどによって情報系システムが同時稼働出来る。そしてoracle側の負荷がA−VX区画に及ぶこともない。さらにもう一つの別のwindows区画ではmetaframeを動かしてやることも出来るのだ。 * 今日メモリ、CPU等はどんどん高性能化(=低価格化)しており、600シリーズと言うだけで高い価格を設定するなどというケチな手法はやめるべきだ。こんな事をしていてはA−VX離れが進むばかりである。 かわりに「サーバ統合方式」を売り物にして、どんどん区画を増やすように持って行けば、管理費用も節約できるので、サーバとしての価値も上がると思う。 * 現在のA−VX on Windowsは実に中途半端だ。 セキュリティに怯え、不安定に怯えつつ、結局はA−VXしか稼働できないのなら、何のためにWindows上で稼働させるのか?? * (追記): 複数区画方式にしたら、下位機種は値段的に難しいだろうナ。。 そこで、 (1)620、630(そんなのあったっけ?)は従来通り、 A−VX on Windows方式にしてオフコン継承をメインとする。低価格。 (2)640以上は、強化マシン。 複数区画方式とする。オープン連携、サーバ統合指向。 (3)680、690は、ACOS下位と統合して、A−VX、ACOS、Windows、HP−UX、linuxが動作できるようにし、徐々にACOSに乗り換えてもらう。 * いずれ、ゆくゆくは(1)を切り捨て、(2)(3)とACOSを一本化する。ホホホ。。。 なんて生き残りのための悪い考えがつい浮かんでしまう。 * ハッと我に返って、「A−VXは永遠です」と信じたい。 がんばれNEC!! | ||
| 2 | Re:A−VX on Windowsは中途半端だ!! | |
| bluelion 2005-3-17 8:53:00
[返信] [編集] S7200ではおもいJOB流しても、全体的に重くはなっても 極端に他のJOBやOSを引きずりませんが Expressだとかなり影響がありますね! ただ私のマシンは古いので最近のは改善してるかもしれませんけど WINDOWS上で稼動するメリットもいくつか感じます 最新のプリンタもWINドライバがある程度まともなら A−VXのSGしだいでも動くのはうれしいです これが、ハード直だとNECさんの対応待ちになってしまいますよね うちの職場ついにA−VXからCSに移行することが決定しました。 趣味と実益を兼ねてソフト開発していたのがこれからは、自宅で趣味一本です いまさらながら古い外付けCMTを購入しました。 640ADにつないで#NEWSRが動いていますが NECの互換性の高さに脱帽です なかみはTEACでしたけど | ||
| 全部読む 最新50 1-100 板のトップ リロード | ||
| ■▲▼ | ||
| 1 | オフコン資産継承する「Express5800/600シリーズ」紹介ページ開設!(2005/02/14) | |
| bluelion 2005-2-18 9:33:00
[返信] [編集] どこまで本気なんでしょうか?(笑) もうすこし 将来像などを示してもらえれば 購入もしやすいんですけど 赤く塗った3倍速いやつを希望 | ||
| 2 | Re:オフコン資産継承する「Express5800/600シリーズ」紹介ページ開設!(2005/02/14) | |
| ターラヤン 2005-2-21 23:30:00
[返信] [編集] > どこまで本気なんでしょうか?(笑) > もうすこし 将来像などを示してもらえれば > 購入もしやすいんですけど > > 赤く塗った3倍速いやつを希望 NECのサイト・8番街 http://www.express.nec.co.jp/index.html のところですね。 ときどき見に行っているのですが全然気が付きませんでした。 今思ったのですが620xi−sってあまり宣伝してませんよね。 最適移行例の一覧表にもない。 | ||
| 3 | Re:オフコン資産継承する「Express5800/600シリーズ」紹介ページ開設!(2005/02/14) | |
| bluelion 2005-2-22 10:21:00
[返信] [編集] リンクしてませんでしたね すみません XI-Sってスタンドアロンモデルですが3台まで端末つながることを考えると以上にコストパフォーマンスよさげですね ただし SMARTやCOBOLが高いから.....トータルではそれなりの金額になるのでしょうけど 宝くじでもあたったらフル装備で遊びたいかも | ||
| 全部読む 最新50 1-100 板のトップ リロード | ||
| ■▲▼ | ||
| 1 | A-VX HPの強化内容の項目にServerW@LLという製品が!! | |
| EXCHANGE 2005-1-31 13:25:00
[返信] [編集] > http://www.ace.comp.nec.co.jp/product/2nd/avx4/avx_home/ > > * 今後、セキュリティ強化に関してはA?VX01だけでなく、 > W2Kサーバ上で稼働しているA?VX4の後期バージョン > についても可能な限り機能追加して欲しいと思います。 > Windowsのセキュリティ問題が深刻化している今日、 > 旧バージョンのA−VXを現在使用しているユーザにとって > 大きな安心感になると思います。 > (Win2003サーバとは少し違う形になるとは > 思いますが。。) > * WindowsUPDATEをかけていないPCからのアクセスを拒否するような形でのサーバ防衛をポリシーベースで可能にする ServerW@LLという製品の説明が A−VXホームページに掲載されました。 NT4.0ベースで稼働している600シリーズにも適用できそうです。 NECさんありがとう!! * でも価格的にかなり高価な感じなのが気になるところです。 このあたりは、DBレプリケーションと同様、基本機能として提供して欲しいところですよネ。 | ||
| 全部読む 最新50 1-100 板のトップ リロード | ||
| 新規投稿 | スレッド表示 | ツリー表示 | 投稿順表示 | i-mode | トップ |
BluesBB ©Sting_Band